<3>「海の精 やきしお」の物語

「海の精 やきしお」食卓ビン60g 454円(税込)
今回は、伊勢神宮に伝わる日本古来の製法を参考にした「海の精 やきしお」。「海の精 あらしお」が完成して、15年あまり経ってからのことです。本物の焼塩を復活させようと科学的な知識を学びながら、試作を繰り返しました。その誕生秘話と製法や技術開発の過程をご紹介します。
お客様の声にお応えするために
前回は伝統海塩(あらしお)を開発することになった経緯をお伝えしましたが、発売後しばらくすると、「あらしお」をお使いいただいている多くのお客さまから、“さらさらと使いやすい「海の精」が欲しい”というお声をいただくようになりました。
伝統海塩「海の精 あらしお」は、海水100%を原料に、天日と平釜で塩の結晶をつくる伝統製法でつくられています。海水由来のニガリ成分(各種の無機塩類)を含み、ただ塩辛いだけでなく、甘さ、旨さ、コクがあります。ニガリの主成分は塩化マグネシウムですが、これには潮解性といって、空気中の水分を吸って溶ける性質があります。そのため塩化マグネシウムを含んだ伝統海塩は、しっとりとしていて、炒って乾かしても、時間がたつと湿気てきます。
精製せず、栄養成分であるマグネシウムを含みながら、さらさらの塩をつくる。これはとても難しいことでした。科学的な知識を学びながら、試作を繰り返し、1999年(平成11年)に「海の精 やきしお」が誕生しました。
伊勢めぐりが大きな前進に
身近に前例もなく、試行錯誤の連続でした。塩専売制が施行された明治以降、焼塩の資料はほとんどなく、焼塩の製造工程を知ることは容易ではありませんでした。それが、伊勢神宮の御塩殿(みしおどの)神社を見学して大きな手がかりを得て、焼塩づくりが前進したのです。
伊勢神宮では、神様にお供えする御饌(みけ)はすべて自給自足によって賄われています。米を食にして、野菜、海産物、必要な機折りなど。その中の一つに塩があり、今なお昔ながらの方法で塩づくりが行われています。塩づくりをする日は決まっていて、鹹水を濃縮する、粗塩を作る、それから焼塩を作るという三つの工程を経て作られます。神様にお供えするのは焼塩なのです。知識として伊勢神宮で塩づくりをしていることは知っていましたが、実際に見たことはありませんでした。
1993年1月、伊勢出身の㈲AMA JAPANの七林さんが一度伊勢神宮を案内したいということで、2~3日伊勢めぐりに行きました。外宮、内宮をお詣りした後に、実際に塩を作っているという、御塩殿(みしおどの)神社にも行ったのです。正月後の時期はずれだったので、誰もいない中、ずっと見て回っていました。すると、人がいたので、声をかけてみたところ、普段着ではありましたが、御塩殿神社の神主さんだったのです。立ち話ではありましたが、実際にそこで塩を作っている人から、焼塩の製造工程を含めた色々な話を聞くことができました。ここで聞いたことを活かそうと思ったのはだいぶ後になってからではありますが、焼塩を完成させることができたのは、七林さんのおかげだと思っています。

伊勢神宮の御塩殿神社
“焼く”と“炒る”の違い
家庭で伝統海塩を土鍋で“炒る”と、しばらくはさらさらと使いやすくても、時間がたつとまた湿気てきます。これはニガリが乾燥しているだけで、潮解性のある塩化マグネシウムが変化していないからです。湿気ないようにするには、“焼く”必要があるのです。けれど、塩化マグネシウムを変化させるということは、成分も変わるということ。「海の精 あらしお」がおいしい塩類バランスだと考えていたため、あまり成分を変えないようにやりたかったのですが、それではさらさらとした焼塩は作れません。そこで考え方を変え、「昔から伝わる“本物の焼塩”を復活させる」ということを目的としたのです。
ポイントは2つ。焼成温度を600度C以上に設定すること、そして焼物の器に入れて焼くこと。
日本古来の製法を参考に
潮解性のある塩化マグネシウムを焼成すると、塩酸ガスと塩化水素が出て、酸化マグネシウムに変わります。そこまで完全に焼き切ると、湿気なくなるのです。それが高温焼成で、「海の精 あらしお」を600度C以上で焼成し、焼塩にしています。
600度Cともなると、完全に焼き物の世界。そこで、焼き物の窯(かま)で焼塩を作る実験をはじめました。研究を始めたばかりのころは、塩酸ガスによって、窯がぼろぼろになってしまい、一つだめにしてしまったこともありました。
産業的に焼塩を作るとなると、焼く時に出る塩酸ガスの処理法も考えなければなりません。毒性はなくとも強い酸性なので、周りに樹木があれば枯れてしまうし、人間が吸えば喉などの粘膜をやられてしまいます。そこで、化学的な原理に基づいて、酸とアルカリで中和させる装置を開発し、まったく無害な廃液として処理する設備を作りました。その設備の周りに生えている木々は、もちろん青々と元気に茂っています。
伊勢神宮の御塩殿神社では、三角すいの素焼きの土器に粗塩(あらしお)を入れて一昼夜焼くそうですが、その焼成には熟練を要すると言います。この方法でニガリを含んだ塩の結晶を焼成すると、塩化マグネシウムが分解され、マグネシウムを含んでいるのに、再び湿気にくい伝統焼塩ができました。
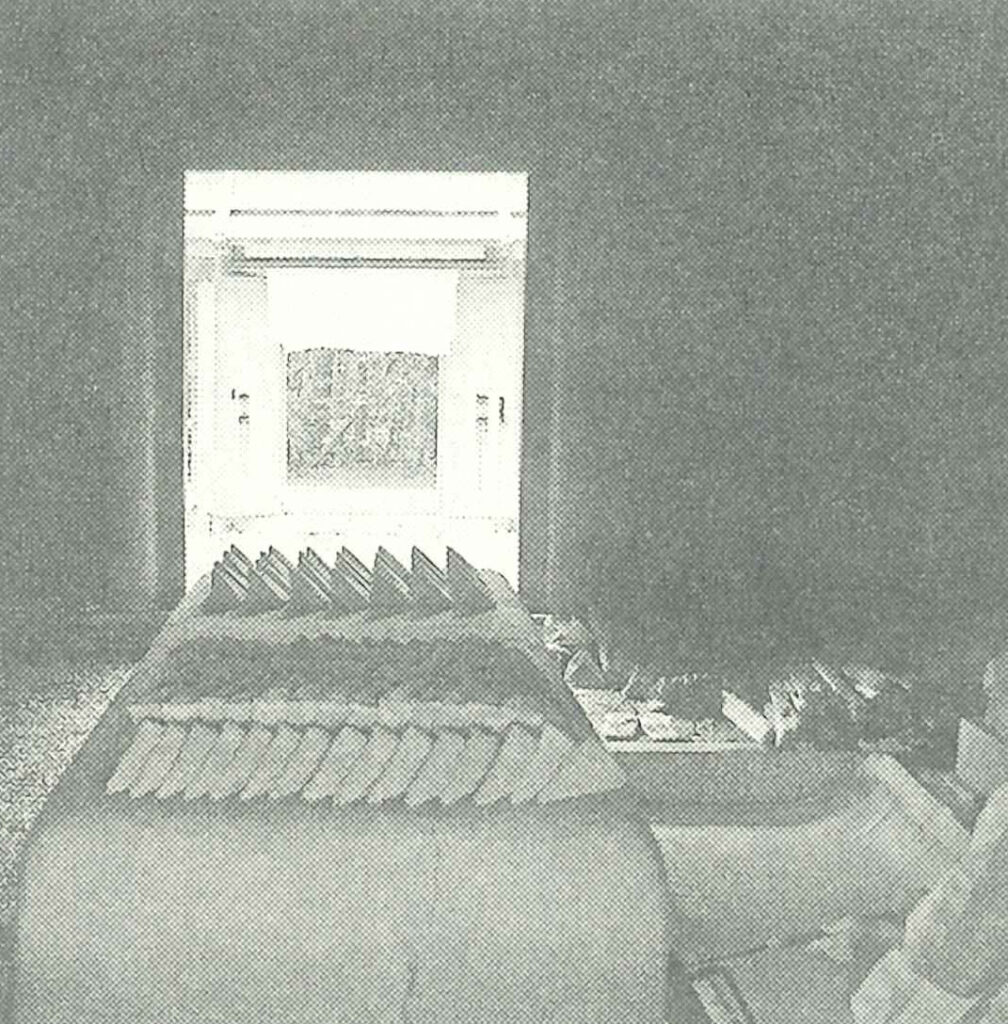
伊勢神宮 御塩焼所での焼固
おいしい苦味も適度に残す
塩化マグネシウムが加水分解を起こす温度には諸説があり、380度Cというのはその一つです。ニガリ成分の多い伝統海塩だと、380度C未満の低温焼成ではあまり加水分解は起こらず、一度はさらさらになっても、また湿気てきてしまいます。潮解性を十分に除いてさらさら感を保つには、600度C以上で焼くことが必要であると考えています。
かといって温度が高ければよいというわけではなく、あまり焼きすぎると、湿気ない代わりに、ニガリの旨味がなくなり、出し殻みたいな味になってしまいます。味もニガリの量も、焼成温度と焼成時間によって微妙に変化します。塩化マグネシウムが持つ“おいしい苦味”が、焼成する中で溶けてしまいます。それを適度に残すことで、コクがあって、旨味を感じられる焼塩の完成です。長年の経験と焼成窯の制御技術によって、ちょうどよいあんばいにコントロールしているのです。
“乗せる塩”としておすすめ
おいしい苦味(塩化マグネシウム)が分解することで、「あらしお」より苦味が減り、マイルドであっさりした味わいになっています。ただ、酸化マグネシウムは水に溶けないので、焼塩を溶かすと白濁します。漬物や味噌づくり、じっくり煮込む料理には、「あらしお」の方が向いています。「やきしお」はテーブルソルトのように、出来上がった料理に味を足したり、つけ塩のように使ったりと、“乗せる塩”としておすすめです。
伊勢神宮に伝わる日本古来の製法を参考に、「海の精 やきしお」を完成させました。マグネシウムを含んでいるのに、さらさらと使いやすく、こんなに味わい深い伝統焼塩は他にないと思っています。
【コラム】焼塩はグルメの食卓塩?
焼塩は食卓塩を必要とする食文化が新しく芽生えた中世ころから広く製造されるようになりました。1合弱の素焼きの壺に粗塩を2日も焼いたもので、厚手の壺にはブランドの刻印が押してありました。近世には京都・大阪をはじめとする関西地方で生産され、各地にもたらされ、祝宴などハレの席の食事に食卓塩として供されました。塩がまだ貴重品な時代、お金持ちのステイタスであり、グルメの塩だったようです。







